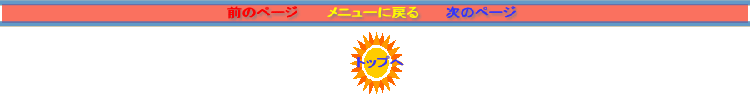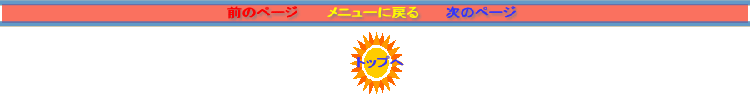
[1-4] [5-8] [9-12] [13-16] [17-20] [21-24] [25-28] [29-32] [33-36] [37-39]
第9回
| インカ帝国とキープとインカ道 |
銀の雪を冠したアンデス山脈の空撮映像が、フォルクローレの哀愁帯びたメロディにのせて、いっそう崇高的な存在のように迫ってくる。ここで使用されている「ハープ」のような音色は、「インディアン・ハープ」としてパラグアイなどで親しまれている民族楽器「アルパ」だと思われる。 ――インカ人はどこからやって来たのか。 という命題を、インカ帝国最盛期の勢力地図などを用いて語られる。 旧大陸の人間が陸続きだったベーリング海峡渡って新大陸にやって来たと言うのが定説だが、それを裏付けるように、新大陸で暮らしている「インディオ」と呼ばれる先住民の子供には、私たち日本人など「モンゴロイド」に共通する「蒙古斑」が見られるのだ。 アニメでも重大な役割を果たした「キープ」について、ワマン・ポマ・アヤラ(ペルーの年代記作家。母は、第10代インカ「トゥパック・ユパンキ」の娘と伝えられる)の描いた挿絵や、1から10までの結び目の写真とともに解説される。 また、インカ帝国には「インカ・ハイウェイ(インカ道=カパック・ナン)」と呼ばれる幅6mの道路が、「山の道」と「海の道」の二つを中心にインカ帝国全土に張り巡らされており、そこを駆け巡る飛脚「チャスキ」によって、帝国内のあらゆる情報、海の幸、山の幸などが皇帝のもとに届けられた。 駅伝のようにインカ道の各所に配置されたチャスキは、東京から岡山の距離に相当する「リマ〜クスコ間」を毎時10キロメートルのスピードで、3日で走り抜けたという。 山の道を行き交うロバの群れや、石の階段を降りてくる親子など、インカ帝国の滅びた今もそれは人々の生活に利用されていることを映像が物語っている。 |
第10回
| インカ帝国の謎 |
B.G.Mは、第6回でも使用された「B.G.M 暗」。 今回のお話は、遺跡・建築の随所に見られる「インカ帝国の謎」。 まずは、太陽の祭り「インティ・ライミ」が開かれることで有名な「サクサイワマン」の映像から。 この砦に使われている石は、一番小さなものでも重さ300トンにもなるものだが、このようなものを「車輪」も知らなかったインカ人たちがどうやって運んだのか。 また、それぞれの石は「カミソリの刃も入る隙間がないほどに」(……これは、とくにインカの建築物について語るとき、よく用いられる表現だが)繋ぎ目がぴったりと合わさっている。 それが単純な四角形ならいざ知らず、十面体、二十面体という複雑な面をもった石をどのようにして正確に結合させたのか。 つぎに、クスコから88kmの北西、「オリャンタイタンボ」の巨石について。 この遺跡で威容を誇っている「6枚の屏風岩」は、重さが600トンを越える想像を絶した代物。 この岩は、対岸の石切り場から採られたものだと言われている。山の急斜面に作られたこの場所まで、これまたどうやって運んできたのかがいっさいの謎。 氏の解説によれば、「巨人」や「悪魔」、はたまた「宇宙人の仕業」だと言う人もいるくらいであるらしい。 そのほかにも、恐らく「クスコ・ロレト通り」に残る「インカの石組み(太陽の処女の館跡)」と思われる映像などが流される。 先のオリャンタイタンボの巨石について、ドクトル順平氏は「丸太を使って運んだ」と述べていたが、「車輪」という概念を持たなかった(といよりむしろ使わなかった?)インカ人が、はたして丸太を使ったのかどうかは疑問である。 |
第11回
| タンボ・バンバの祭り |
「タンボ」とは、「宿場」のこと。 インカ道の随所には、このような宿場が数多く設けられていた。 「タンボ・バンバ」と呼ばれるこの町で行われる、祭りの様子が紹介される。 この祭りは、野生のコンドルを雄牛の背中にくくりつけて戦わせるという、いわゆる「コンドル・ラチ」の祭り。 この回のアニメでは、シアが幼いときに飼っていたコンドルの「パト」が登場した。 ラチとは「引っ掻く、傷つける」などの意味を持った言葉で、その名のとおり、鋭いコンドルのくちばしが暴れ狂った雄牛の身体を傷つける。 今では野生のコンドルを使うことはめったになく、この町ではその代わりに、願い事を込めた色とりどりの布を取り付けて、雄牛と村の男たちが戦うという儀式に変貌している。 これは、雄牛(スペイン)とコンドル(インカ)の戦いを象徴するかのような祭りで、しばしば、スペインに征服されたインカの復讐のような形で描かれる。 ドクトル順平氏もそのように解説している。 しかし、ある書物によると、先住民よりもメスティーソ系の村々にこの「伝統」が残されていることが多いという。 実際はその逆で、白人または白人系メスティーソたちが、宗教的に先住民の人々を支配していく上での祭りなのではないかというのがその考えだ。 祭りに使われたコンドルは、例外もあるが、そのほとんどが野に放たれる前に瀕死となってしまうのである。 これは、コンドルを「聖鳥」としたインカの人々の思想に相反することではないのだろうか。 |
第12回
| 雲の都マチュ・ピチュ |
アニメの舞台は「老いたる峰」……マチュ・ピチュへ。 今回は、その「マチュ・ピチュ」についての紹介。 霧に包まれた空中都市「マチュ・ピチュ」の映像からはじまり、クスコからの高原列車の警笛が、のんびりと渓谷に響き渡る。 スペインに追われたインカはクスコを捨て、アンデスの山奥に「ビルカバンバ」を作った。 ウルバンバ川からアマゾン源流へと遡る途中にあるこの都市は、15000人もの人々が暮らすことのできる規模を持っていた。 1911年。アメリカの探検家「ハイラム・ビンガム」によって発見されたこの遺跡こそが、落ち延びたインカ人たちが立て篭もった「ビルカバンバ」だと噂された。ハイラム・ビンガムは、その傍らの山にちなんで「マチュ・ピチュ」と名づけた。(マチュは「老人」、ピチュは「峰」という意味。現在マチュ・ピチュは、ビルカバンバではないと考えられている) マチュ・ピチュの地下への階段を降りてゆくと、そこに、口を開き、苦しそうに顔を覆っている女性のミイラが画面いっぱいに映し出される。 マチュ・ピチュから発見された173体のミイラのうち、150体以上が「若い女性」のものだった。 そのどれもが苦痛に歪んだ顔をしていたという。 その女性たちは「太陽の処女(アクリャ)」ではないかと考えられ、何らかの理由でインカがこの都市を捨てることになったとき、秘密が漏れないようにアクリャたちを殺したのだという。 しかし、その真相もマチュ・ピチュが滅んだ理由も、永遠に苦しみつづけたままの彼女らとともに謎である。 彼女たちは、いったいなにを訴えかけているのだろうか。 |